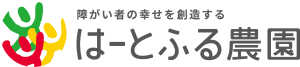サンテレホン株式会社様
管理本部 人事総務部
山 内 淳 様
障がい者雇用に関する課題
- 自社雇用ベースで長年、対応してきたが、長期雇用できている方は限定的
専門知識を求められる仕事が多く、障がい特性や条件が限定されるのが現状 - 現場の理解、協力を得ることが難しい
はーとふる農園を利用してよかったこと
- 様々な障がいを持つ4名のメンバーが就業、安定して継続できるようになりダイバーシティが促進
- 社長が農園の就業に理解がある。社長が来園することで就業者のモチベーションが向上し、社内に障がい者雇用の認識が広がる
- 障がい者の従業員に、自社主催の展示会を見学。社員からの声がけなどの交流により、帰属意識が向上。自社主催の展示会後の取引先とのパーティーでは、農園で収穫したベビーリーフを使った料理を提供し、障がい者雇用推進を内外に PR
- 障がい者の方の成長がみられること

1948年創業の情報通信機器・部材の専門商社として、国内外約500社の商品仕入れ先をもつサンテレホン株式会社 様(本社:東京都中央区日本橋箱崎36番2号)。
2021年11月からはーとふる農園をご利用いただいており、現在4名の方が働いていらっしゃいます。障がい者雇用については、社内では本業での仕事の切り出しが難しく、現場での負担が大きく困難な中、はーとふる農園の利用に踏み切られた、とのことです。その後、状況はどのように改善されたのでしょうか。
管理本部 人事総務部 山内 淳 様にお話を伺いました。
― 障がい者雇用への取り組みはいつ頃からされていますか?
私は、2021年に中途で入社したのですが、それまで障がい者雇用については自社業務での雇用ベースで取り組んできたが、なかなかうまくいかず苦労していたようです。現在も、本社での雇用は、ご自身の障がいをコントロールできる方が数名働いていただいているのにとどまっています。
当社は専門性の高いICT関係の商品を扱っているので、業務内容を障がい者の方へ覚えていただくのはかなりハードルが高く、また何かルーティン的な事務 仕事をうまく切り出して…とも考えたようですが、IT化が進むとそれもなかなか難しいという状況で苦慮していたと聞いています。
― どのようにして、はーとふる農園を知りましたか?
当時、法定雇用率を大きく割り込み、当局から指導の対象となりそうな状況で、至急対策を講じる必要がありました。
前述のような経験から外部の障がい者雇用のサービスの検討に絞り、調査をスタートしました。都市型のサテライトオフィスや農園のサービスが広まりつつあった時期です。都市型オフィスでは、仕事の切り出しが難しいという問題があり、農園に絞りました。屋内型と屋外型がありましたが、現場を見学させてもらい、働いている方の様子も拝見して屋外で陽の光を浴びて健康的にやった方がよさそうだ、と思いました。
その時に、『はーとふる農園 愛川』に出会いました。働いている方が、笑顔で活き活きと働いている感じが印象的でした。また、営業の方の「働くだけでなく、障がい者の成長をサポートしていきたい」という姿勢に共感しました。
ビニールハウスの農園ということで、当時から夏の暑さはちょっと気になっていたのですが、それでも、屋内栽培の閉鎖的な施設よりも屋外の方が心身の健康面でやはりいいだろう、ということですね。
正直言って、コスト面では似たような価格帯の他社もあり、ずば抜けて、ということではなかったんですが、「設備をもたなくてよい」・「管理者の直接雇用がない」という点も、採用の後押しとなりました。
― はーとふる農園の社員の方とは、どのようにコミュケーションをとっていますか?
平均して2カ月に一度程度は訪問し、就業者と個別面談を行っています。面談では、健康面や就業面、そのほか問題がないか確認したり、プライベートの雑談話など行っています。普段は、農園のスタッフの方が必要な対応を行ってくださり、なにかあれば、すぐ連絡いただけるので安心しています。
また、猛暑日の自己学習課題として課題図書を数冊渡してあり、その読書感想を聞いたり、周囲とのコミュケーションの取り方についてアドバイスすることもあります。
― 社内での関心はいかがでしょうか?

社長が、年に一回程度、来園します。ビニールハウスの中で就業者と面談します。メンバーはその時は緊張しているのですが、あとで話を聞くと「社長が(農園に)来てくれる会社など他にないです」といい、モチベーション向上につながっている様子がうかがえます。社長は折に触れ社内の会議などでも、農園の話もしてもらえるので、社内での障がい者雇用への理解が徐々に深まっていると思います。
今は収穫物のベビーリーフを近所のスーパーで販売することができているのですが、始めの頃は、袋詰めを2カ月に1回程度、本社へ送っていただいて無償で社内配布をしていました。社内掲示板「神奈川県のはーとふる農園というところでうちの社員が作った野菜ですよ、無償です。よかったら食べた感想を寄せてください」と告知すると「おいしかった」の声とサラダの写真が寄せられたので、写真とメッセージをレターにして農園の従業員に渡しました。それはうれしかったようです。
また、定期的に取引先向けに商品展示会を開催しているのですが、その際、取引先とのパーティーがホテルであります。ホテルに頼んで、ベビーリーフを使った「サラダ」や「おひたし」などの料理を提供してもらっています。「我社の、障がい者雇用の神奈川県のはーとふる農園で取れた野菜です」と宣伝させてもらって提供することで、社内外に自然な形で障がい者雇用の推進を PR できています。
東京での展示会には、はーとふる農園に従事しているメンバー皆で見学に行きます。自分の会社の事業についても理解してもらっています。
― 社内から「はーとふる農園」の導入に対する反対意見などはなかったですか?
反対意見というほどのことではありませんでしたが、当社の業種と違う「農園で働いてもらうこと」に違和感を感じた方もいました。農園作業の安全性についての懸念をご意見をいただいたこともあります。
当社の現場業務においては、仕事の内容が難しく、切り出しも容易ではない事や、農園には現場の管理者や作業の指導の方がいて、就業者をサポートしてもらえること、などをお話しして理解してもらいました。
私も、本来自社の業務での雇用が筋であることは理解していますし、将来的にはそれを検討する時期も来ると思います。しかし、いま当社が障がい者雇用の社会的責任を果たすためには、はーとふる農園さんの力を借りて、一緒にやっていくっていうのが、今取り得るベターな選択であると考えています。
― はーとふる農園で働く 4 人の従業員の皆様のご様子はいかがでしょうか。
多様な障がい特性の方を採用しています。多少の人間関係の問題などの話が出るときもありますが、農園の管理者やスタッフの方々がうまく対応してくださり、大きなトラブルはないと思っています。
先ほど話しました展示会へ見学に連れて行ったことで、本業をはじめて目の当たりにして興味深そうにしていました。
その会場では、社員から「野菜たべたよ」「おいしかったよ」などと声がかかるなど、帰属意識が高まる機会にもなったと思います。
農園では、いままでずっとベビーリーフのみの取り組みだったのですが、新しい野菜栽培の試行錯誤がスタートしていて、レタス系とかミニトマト系に挑戦しています。うまくいったりいかなかったりしているみたいです。
そのように取り組み内容がステップアップしていけることはよいことと思います。
― はーとふる農園のサポートで要望はございますか?
はーとふる農園が、彼らにとって一生居るところではなくて、ここで集団での立ち振る舞いとか、労働というものを学んで、はーとふる農園を卒業して次のステップアップに行ける、というようなキャリアパスのようなものができると、いいんだろうな、と思います。
それは、はーとふる農園さんに期待するところですが、私たちの課題であるとは思います。

―今後、はーとふる農園の障がい者の方とやってみたいことなどはありますか。
今後の話ですが、熱中症アラートがでる日があらかじめ分れば、農園の会議室をお借りして、コミュニケーションやマナー的な内容のミニ研修を実施できると、メンバーの更なる成長に寄与できるかなと思っています。
また、展示会だけでなく、彼らが当社の仕事や社員をより知る機会や接する機会を作っていきたいですね。社員ですので。
―障がい者雇用に悩む企業様にメッセージがあればいただけますか。
皆さま課題を感じてらっしゃると思いますが、自社で雇用するのはいろいろ考えても難しい―という状況であれば、一度、先入観をもたず、はーとふる農園を見学してみたらいかがでしょうか?
農園での雇用について、本業とは違うので、とネガティブなイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に農園で生き生きと働いている就業者をご覧になると、皆さまがイメージしていた「農園労働」という印象とは、少し違う感じを持たれると思います。
はーとふる農園と一緒に取り組めることができれば、社会的責任は果たせるし、就業者もやりがいを持って働いてくれれば、お互い WinWin になれる、と私たちは思っています。
― 最後に、この3年間で印象に残っていることはあれば教えてください。
農園では、当社のメンバーは、指導者の方の指導の元、チームで仕事をしています。個人で黙々とやる場面もありますが、連携して行う業務もあるのでお互いに声がけしながら進めることになります。
困ったことがあれば、自分から仲間に相談したり、スタッフの方に話をしなくてはなりません。そうすると、メンバー誰もが、入園時に比べてコミュニケーション能力が向上します。特に就業者個別面談の時にその成長を確認できます。
これも、はーとふる農園のおかげだと思っています。
またベビーリーフが、自宅近隣のスーパーマーケットで販売されているのを目にすることもあるそうです。自分たちの栽培した野菜が、ご家庭の食卓にのぼることが、自分たちの仕事の価値を感じる大切なことと思います。彼らのやりがいにもつながっていることと思います。
― 今日は貴重なお話をたいへんにありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
2024年11月18日インタビュー
※掲載の数値情報・名称等は、インタービュー時のものです。
サンテレホン株式会社
長 尾 様

視力に障がいをお持ちの長尾様。サンテレホン株式会社の社員として、はーとふる農園で農業に従事されています。お話を伺いました。
―はーとふる農園での就労以前は、お仕事をされていましたか?
B型支援事業所に通所しておりました。プラレールの電車の屋根の部分を、塗装しやすいように、台紙に両面テープを貼り付けて一定の間隔に置いていく作業とか、女性のヘアゴムやヘアピンを決められた本数数えて専用のケースに入れていく、という作業をしていました。細かい作業で目を酷使するので、頭痛や疲労がひどく、単純で同じ作業の繰り返しなこともあって、休みがちでした。
―はーとふる農園はどのようなきっかけで知りましたか?
既に、はーとふる農園さんで、(別の企業さんですが)働いている親友がおりまして。「一度、はーとふる農園さんに見学実習してみてはどうか」とおっしゃってくださったんで。
―見学実習をしてみて、いかがでしたか?
もう、やってみたいなっていう感じでした。B型支援事業所の仕事は座ってる作業だったので、自分は動いていたいなっていうのがあったので、見学、実習を受けてみて実習最終日には「はーとふる農園さんで就労したいです」と伝えました。
―農業という未経験の仕事に対する戸惑いはなかったのでしょうか。
種を撒くので、自分は視力障がいがあるので、見え方とかやり方とか「どうかな」とも思ったんですけど、実習でやってみたら問題なくやれたので、やってみたいな、と思いました。
―はーとふる農園での仕事で楽しいと思うことはどんなことですか?

B型支援事業所の時は、「もう仕事か…」と思うことも正直ありました。体を動かしていない割には疲れたり、結構、目も酷使していて毎日ちょっと頭痛がするので、薬を飲んで「外、行きます」とか言ってたんですけど、はーとふる農園さんに移ってからは、そういうことが全くないです。
はじめの頃は、さすがに種をまく時に、結構、慎重に目を酷使して目が疲れて痛いな、という時もありましたが、農業指導員さんや管理者さんに「こういう風にするといいよ」と教えていただいて、そのやり方をやってみたら、疲れなくなりました。特に農業指導員さんとは、個人的に話したりすることもないのに、私の作業を見ただけで「長尾さん、こうやった方がいいよ」とすぐにおっしゃってくださいます。同系色がどうしても見にくいので、砂と種の色が同じような時は、さすがに、ちょっとたいへんですが。
種を植えた後、雑草を取りますが、もう一人の男性の方も、ちょっと目が悪いので、雑草が小さいうちはどうしても見にくいんです。ですが、管理者さんから「雑草が成長してからでいいよ」と言っていただいて。それに、チームの女性陣がもうバンバン採っちゃうから、「そのままにしとけば、抜いてくれるから」っていう形で。不得意なことはやってくれます。
その後、収穫のサイズのものを選んで取っていきます。「汚れがついていないか」とか「虫がついていないか」とか、そういうのを確認して収穫します。
「自分が買う側になったら、この、いま自分がつまんでいる作物を買うか」と考えながらやっています。口に入れるものなので。そこは自分だけじゃなくて、たぶん全企業の方々が気をつけていることだと思います。
―ご家族の方は、何かおっしゃっていらっしゃいますか?
B型支援事業所の時は、結構、休みがちで心配をかけていました。父が心臓を患ってしまったのですが、いままでは、どうしても工賃だったので援助できなくて。はーとふる農園さんに移ってからは給料になったので、幾分か援助できているので、すごい助かっている、と言われました。
―これから就職したい、と考えている方にアドバイスをいただけますか?
自分で種を蒔いて、それが日々成長していって収穫できるというのは、すごい満足感っていうか、仕事を続けていこうという気持ちに繋がるんじゃないかな、と思います。
「今日、種まいたからどのくらい成長してるかな、明日ちょっと頑張って行ってみようか」と。
仕事は「これができていない(例えば種がちゃんと蒔けていないとか)!」と怒るような管理者さんや同僚もいないですし、できないのであれば、別の作業を振り分けてもらうとか、自分のように農業指導員さんが見ている中でやってみると「こうしたらうまくいくよ」って言ってもらえたりするので。
苦手な作業は誰にでもあると思うんですけど、「ここを、もうちょっとこうやったら上手くなる」など、声を掛け合ってやっているので、大丈夫です。
(自分の場合も、どうしても砂が見づらくて量がわかりづらいときがあるですが、「こっちちょっと少ないですよ、こっちが多いです」と言ってもらうと「こっちの多いところからこっちへ移せばいいんだ」ってわかるから、やりやすい。)

― 長時間、お話を聞かせていただき、ありがとうございました。どうぞご自愛いただき、長く勤務していただくことを心より願っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
2024年11月18日インタビュー
※掲載の数値情報・名称等は、インタービュー時のものです。