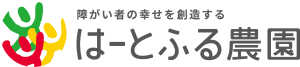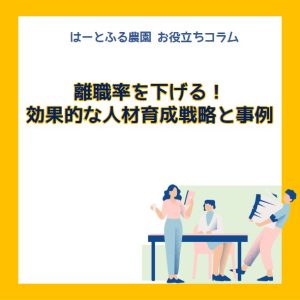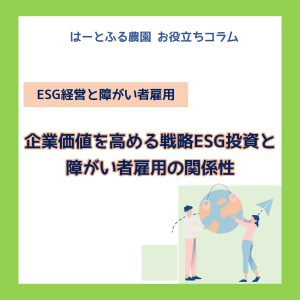ハラスメント対策の最新動向と企業の対応策
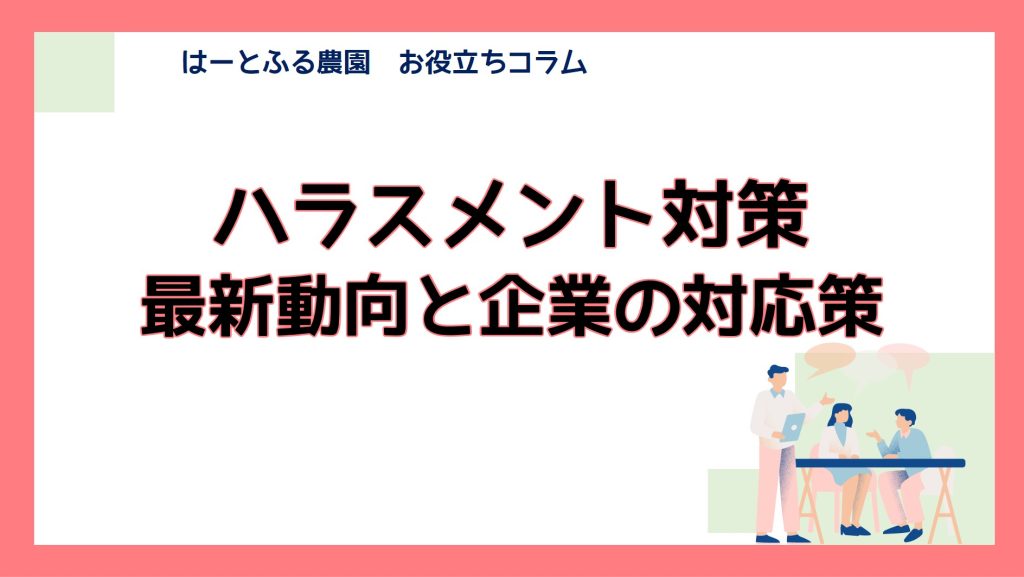
職場環境の改善や従業員のメンタルヘルス維持のため、多くの企業が積極的な対策を講じるようになりました。
特に、2022年4月に施行されたパワーハラスメント防止措置の義務化により、企業にはより具体的な対応が求められています。
さらに、企業のリスクマネジメントの観点からも、ハラスメントを未然に防ぐための研修や相談窓口の整備が不可欠です。
そこで本記事では、ハラスメント対策の最新動向と、企業が取り組むべき実践的な対応策について解説します。
ハラスメントとは?
ハラスメント(harassment)とは、特定の個人や集団に対して不適切な言動や行動を繰り返し、精神的・身体的に害を与える行為を指します。もともと「harassment」は、「嫌がらせ」や「迷惑行為」を表す英単語です。
職場においてハラスメントが発生すれば、従業員のパフォーマンス低下やメンタルヘルスの悪化、企業の評判リスクなどに直結します。
日本では、厚生労働省が「職場におけるハラスメント関係指針」を策定し、企業に防止措置の義務を課すなど、ハラスメント対策が法的にも強化されています。特に、2022年4月からパワーハラスメント防止措置が中小企業にも義務化され、企業はより具体的な対応が求められるようになりました。
ハラスメントを放置すると、離職率の増加や労働生産性の低下、訴訟リスクなど、企業にとって大きな損害をもたらす恐れがあります。このため、経営者や人事担当者は、未然防止のための体制整備や研修の実施などの対策を積極的に進める必要があります。
ハラスメントの種類
職場で発生するハラスメントにはさまざまな形態があり、いずれも企業の労働環境や生産性に深刻な影響を与えます。
ここでは、主なハラスメントの種類について解説します。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、性的な言動によって相手を不快にさせる行為を指します。
職場では、上司から部下への発言だけでなく、同僚間や取引先との間でも発生する可能性があります。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)の具体例
・性的な冗談や不適切な発言を繰り返す
・不必要に身体を触る、または過度に接近する
・業務上の立場を利用した性的関係の強要
・社内の異性に対して外見に関する不適切なコメントをする
パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメント(パワハラ)とは、職場内での権力や立場を利用して、精神的・身体的に相手を攻撃する行為 です。
特に、管理職が部下に対して行うケースが多いですが、逆に部下から上司への嫌がらせ(逆パワハラ)も問題視されています。
パワーハラスメント(パワハラ)具体例
・過度な叱責や威圧的な態度
・意図的に仕事を与えず、孤立させる
・過度なノルマを課し、達成できないと罰を科す
・上司が部下に通常の注意をしただけなのに、「パワハラを受けた」と労災申請される
マタニティ・パタニティハラスメント(マタハラ・パタハラ)
マタニティハラスメント(マタハラ)およびパタニティハラスメント(パタハラ)とは、妊娠・出産・育児に関連して不当な扱いをする行為を指します。
マタニティ・パタニティハラスメント(マタハラ・パタハラ)具体例
・妊娠や育児休業を理由に降格・異動を強要する
・「育休を取るなんて甘えだ」といった発言をする
・復職後にキャリアの成長を妨げる措置を取る
・育児休業の取得を理由に契約更新を拒否する
カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先から従業員に対して行われる不当な要求や嫌がらせを指します。
カスタマーハラスメント(カスハラ)の具体例
・不当なクレームや暴言の繰り返し
・従業員に対する過度な要求や土下座の強要
・営業時間外の対応を強いる
・個人情報の公開や脅迫行為
モラルハラスメント(モラハラ)
モラルハラスメント(モラハラ)とは、精神的な攻撃や人格を否定する言動を指します。
特に目に見えにくいため、対策が遅れやすいというのが特徴です。
モラルハラスメント(モラハラ)の具体例
・陰口や悪口を広める
・特定の社員を意図的に無視する
・業務上必要な情報を意図的に渡さない
・人格を否定するような発言を繰り返す
アルコールハラスメント(アルハラ)
アルコールハラスメント(アルハラ)とは、酒席での迷惑行為や飲酒の強要などを指します。
アルコールハラスメント(アルハラ)の具体例
・飲めない人に対して無理に飲酒を勧める
・一気飲みを強制する
・酒席でのセクハラや暴力行為
・酔った勢いでの不適切な発言や行動
スメルハラスメント(スメハラ)
スメルハラスメント(スメハラ)とは、職場内での体臭や香水などの強い匂いが原因で周囲に不快感を与える行為のことです。
スメルハラスメント(スメハラ)の具体例
・過度に強い香水の使用
・体臭が原因で周囲に不快感を与える
・タバコや食べ物の臭いが服に残ったまま出勤する
ハラスメント対策の最新動向と企業の対応策
厚生労働省の「令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)」によれば、企業におけるハラスメントに対する取組状況として、「相談窓口の設置と周知」の割合が最も高く、約7割以上の企業が実施しているといいます。
次いで多いのが「ハラスメントの内容、職場におけるハラスメントをなくす旨の方針の明確化と周知・啓発」で、約6割以上の企業が実施しています。
全業種の中では、取組を実施している割合が他業種より高いのが「金融業、保険業」「複合サービス業」となっています。
また、ハラスメントに対する取り組みの副次的効果としては、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」の割合が最も高く、39.1%で、次いで「会社への信頼感が高まる」(34.7%)」という結果になっています。
ハラスメントに関して企業に求められる対応
厚生労働省はまた、ハラスメントに関して企業に求められる対応について「ハラスメントに関する施策及び現状」にまとめています。
同資料の中で「事業主が雇用管理上講ずべき措置の主な内容」として、下記の4点が挙げられています。
事業主の方針の明確化及びその周知啓発
ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、管理監督者を含む労働者への周知啓発。行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口の周知。発生のおそれがある場合やハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応。
職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
事実関係を迅速かつ正確に確認。事実関係の確認後は、速やかに被害者に対する配慮のための措置とともに、行為者に対する措置を適切に対応する。再発防止に向けた措置を講ずる。
併せて講ずべき措置
プライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知。事業主に相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発をする。
企業が取り組むべきハラスメント対策
ここでは、上記のハラスメント対策を具体的な施策に落とし込んで解説します。
加害者にならないための教育と意識改革
企業がハラスメントを防ぐためには、従業員一人ひとりが「加害者にならない」という意識を持つことが重要です。
そのため、 定期的な研修や意識改革プログラムの実施が不可欠です。
ハラスメント研修の実施
全従業員向けに定期的なハラスメント研修を実施し、どのような行為がハラスメントに該当するのかを明確に伝えましょう。
特に、管理職向けの研修では「指導」と「ハラスメント」の違いを理解させることが重要です。
職場でのロールプレイング
ハラスメントの具体的な事例をもとに、ロールプレイを通じて適切な対応を学ぶ機会を設けると、実際の職場での行動に活かしやすくなります。
日常的なフィードバックの仕組み化
部下とのコミュニケーションが不足するとパワハラの温床となるため、上司と部下が定期的に意見を交換できる「1on1ミーティング」などの仕組みを導入すると効果的です。
ハラスメント防止ポスターの掲示
ハラスメントの定義や禁止事項を職場に掲示し、従業員が常に意識できるようにします。
被害者を守るための相談窓口の設置と活用
ハラスメント被害に遭った従業員が安心して相談できる環境を整えることが、企業にとって重要な責務の一つです。
適切な相談窓口の設置と、その活用が被害者の心理的負担を軽減し、迅速な問題解決につながります。
ハラスメント研修の実施
全従業員向けに定期的なハラスメント研修を実施し、どのような行為がハラスメントに該当するのかを明確に伝えましょう。
特に、管理職向けの研修では「指導」と「ハラスメント」の違いを理解させることが重要です。
社内相談窓口の設置
従業員が気軽に相談できる窓口を社内に設置します。
特に、相談しやすい雰囲気作りが重要です。
相談担当者の専門教育
ハラスメント問題に対応する相談担当者には、適切なカウンセリングスキルや対応スキルを習得させるための研修を受けさせましょう。
匿名相談の受付体制の整備
匿名でも相談できる仕組みを導入することで、被害者が安心して問題を報告できる環境を作りましょう。
オンラインのチャット相談窓口も有効です。
ハラスメント相談窓口の利用方法を全従業員に周知する
「どこに相談すれば良いのか」「どのような対応が受けられるのか」を明確に伝えることで、相談しやすい環境を作ります。
第三者機関や外部相談窓口の活用
社内の相談窓口だけでは、 適切な対応が難しいケースもあります。
特に、相談者が社内の担当者に不信感を持っている場合や、公平性を保つ必要がある場合には、 外部の専門機関との連携が効果的です。
外部のハラスメント専門機関と契約する
社内で解決が難しい場合に備え、ハラスメント問題に詳しい専門機関(労働局や弁護士事務所)と連携しましょう。
産業カウンセラーやメンタルヘルス相談の活用
ハラスメント被害者の心理的なケアを目的として、外部のカウンセリングサービスと提携し、専門家のサポートを受けられる体制を整備します。
第三者によるハラスメント調査の実施
公平性を確保するために、外部専門家が調査を担当し、適切な判断を行う仕組みを導入します。
外部相談窓口の情報を従業員に提供する
「外部の相談窓口を利用できる」ことを従業員に周知し、企業外の第三者に相談できる選択肢を提示しましょう。
産業カウンセラーやメンタルヘルス相談の活用
ハラスメント被害者の心理的なケアを目的として、外部のカウンセリングサービスと提携し、専門家のサポートを受けられる体制を整備します。
ハラスメント防止のための企業文化の構築
ハラスメントが発生しない企業文化を作るには、「ハラスメントを許さない」という価値観を全社員に浸透させることが不可欠 です。
そのためには、職場の環境や評価制度の改善が求められます。
「心理的安全性」が高い職場の実現
従業員が 安心して意見を言える職場環境を作ることで、ハラスメントが発生しにくくなります。
チームビルディング研修の実施や、対話の場を設けることなどが効果的です。
フラットなコミュニケーションを促進
上下関係に依存しすぎる文化はハラスメントの温床になるため、役職を超えたオープンな対話の機会を増やすことが大切です。
多様性を尊重する社風の推進
年齢、性別、国籍などの多様性を尊重するために、ダイバーシティ&インクルージョンの研修を実施し、偏見を持たない職場づくり を推進しましょう。
ハラスメント防止のための社内イベント開催
定期的に「ハラスメントを考える日」などの社内イベントを開催し、従業員がハラスメント問題について意識を高める機会を作ります。
人事評価の透明性を向上
上司の評価だけでなく、同僚や部下からのフィードバックを活用した360度評価を導入し、不公平な評価によるハラスメントの発生を防ぎましょう。
まとめ
ハラスメントを防ぐためには、 企業が一丸となって「加害者を生まない仕組み」「被害者を守る体制」「再発を防ぐ企業文化」の3つを構築することが不可欠です。
日本では、ハラスメント防止に関する法規制が強化され、企業に求められる責任も増しています。
ダイバーシティやインクルージョンの観点からも、ハラスメント防止は企業経営の重要なテーマとなっています。従業員の価値観が多様化する中で、企業には「一人ひとりが尊重される職場環境」を整備する責任が求められます。
従業員が安心して働ける環境を整えることで、企業のブランド価値向上や生産性の向上にもつながります。
本記事が、ハラスメント対策をより強化し、持続可能な企業経営を実現するための一助になれば幸いです。