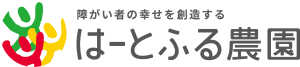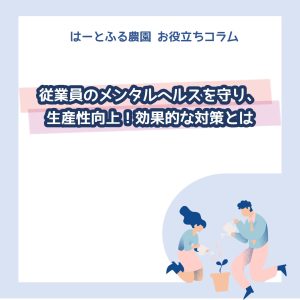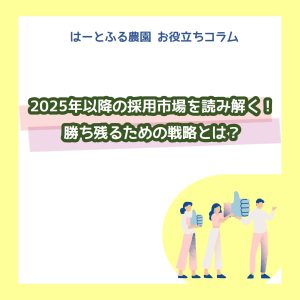障がい者の合理的配慮について、裁判事例をもとに解説
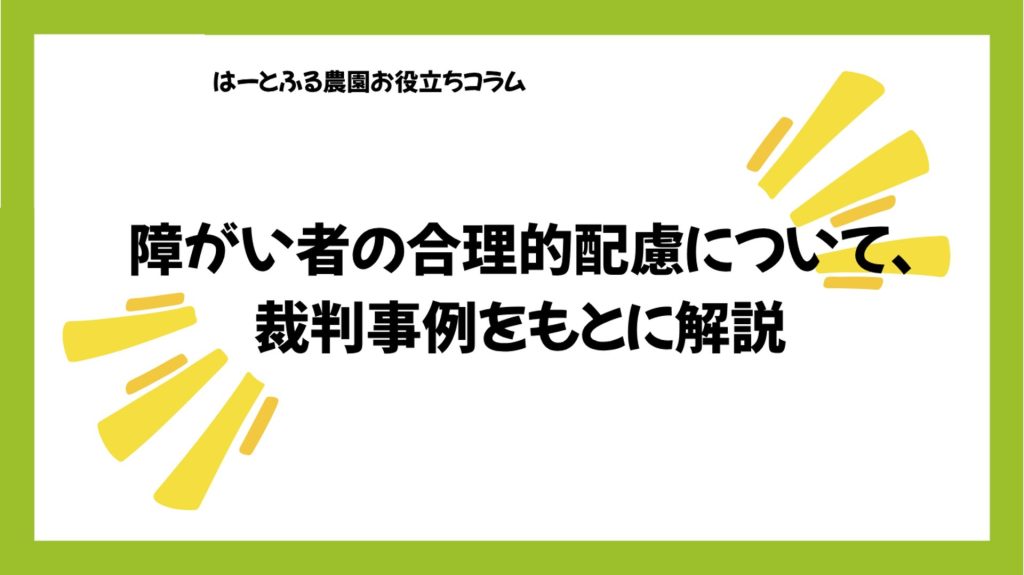
障がい者雇用の現場では、合理的配慮のあり方が重要なテーマとなっています。
企業が配慮を怠った場合、法的な責任を問われるケースもあり、その判断基準を理解することは人事担当者・経営層にとって不可欠です。
近年では、判例を通じて「どのような配慮が求められるのか」が具体的に示されるようになってきました。
特に「Man to Man Animo事件」の判決は、企業が障がいのある従業員に対してどのような配慮義務を負うのか、注目を集めました。
そこで、この記事では、判例を通じて合理的配慮の法的枠組みを読み解きながら、企業が取るべき対応を考察します。
合理的配慮とは?
障がい者雇用において、企業が理解し、実践しなければならないのが「合理的配慮」です。
合理的配慮とは、障がいのある方が社会で活動する際に生じる不便や障壁をなくすために、必要なサポートや環境の工夫を行うことです。
合理的配慮の考え方は、「障害の個人モデル(医学モデル)」ではなく、「障害の社会モデル」に基づいています。
たとえば、車いすの方が階段を上がることが困難な場合、障害を「足を動かすことが困難」と捉えるのが個人モデルです。
それに対し、社会モデルでは「階段にスロープがついていない社会環境」が障害と見なされます。
合理的配慮は、この社会的なバリアを取り除くために必要なものです。
障害者差別解消法と合理的配慮
日本においては、平成28(2016年)に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が合理的配慮の根拠となります。
同法によって、事業者(企業)は合理的配慮の提供が義務づけられました。
障がい者が何らかの対応を求めた場合に、企業は負担が重すぎない範囲で対応する必要があるのです。
企業に求められる配慮の内容
企業に求められる配慮の内容は、多岐にわたります。
たとえば、次のようなものが考えられます。
・勤務時間の調整…フレックスタイム制や短時間勤務の導入。
・業務の見直し…業務を細かく分析・分解し、マニュアル化することで、対応可能な業務を創出・設計する。
・物理的な環境整備…Webアクセシビリティの対応(スクリーンリーダーへの対応など)や、コミュニケーションを支援するためのツールの提供。
・サポート体制の構築…定期的な面談や、気軽に相談できる窓口担当者(メンター)の設置。
配慮が「合理的」であるかどうかは、企業の業務への影響や財政的な負担とのバランスを考慮して判断します。
過度な負担が想定される場には、本人と十分に対話し、代替案を検討することが重要です。
障がい者への合理的配慮に関する裁判事例(Man to Man Animo事件)
では、実際の裁判事例「Man to Man Animo事件」をもとに、障がい者の合理的配慮について、考えていきましょう。
事案の概要
「Man to Man Animo事件」とは、「高次脳機能障害」と「強迫性障害」を持つAさんが、勤務先であるMan to Man Animo株式会社が合理的配慮義務に違反したと主張。損害賠償を求めた事案です。
訴えの提起
Aさんは交通事故により、「高次脳機能障害」や「強迫性障害」をはじめ、さまざまな障害を有するようになりました。
平成20(2008年)年6月18日、Aさんは同社に各障害の状況を伝えた上で期間の定めのある雇用契約を締結しました。
同時に、同社に対して、配慮が必要な下記の事項について、申入れを行っていました。
①腰を痛めているため、スニーカーなどの負担をかけない履物で仕事をしたい
②スニーカーしか履けないため、スーツやブラウスを着用できないことから、服装の自由を認めて欲しい
③業務指示について、指示者は1人にして欲しい
④新しい仕事は1日1つまでにして欲しい
⑤強迫性障害のため、トイレに時間がかかることを了承して欲しい
Aさんは、雇用契約を更新しながら勤務していましたが、平成27(2015)年1月20日以降、休職。
その後、Aさんと同社の関係者や臨床心理士、ハローワークの担当者、障害者職業センターの担当者などで話し合いの場を設けましたが話し合いはまとまらず、平成28(2016)年9月に退職に至りました。
争点
Aさんは、同社が障害のあるAさんに対して提供すべき合理的配慮義務に違反したとして、同社に500万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
争点は、同社がAさんに対して、障害特性に応じた合理的配慮義務を負っていたかどうかです。
判決の要旨
裁判所が、同社がAさんに対して配慮義務を負っていたか否かを検討した結果、次のような判断がなされました。
・腰を痛めていることは、高次脳機能障害及び強迫性障害によりもたらされたものとは直ちに認められないものの、Aさんは、入社当初から履物に関する配慮を求める旨を申し出ており、同社はこれを認識して雇用したことから、履物に対する配慮は、合理的配慮に準じるものとして扱うのが相当である。
・Aさんの主張する「ブラウス着用の強要」「くしゃみの際に手を当てることの強要」「業務指示者の突然の変更」「業務の突然の変更」「スーツ着用の強要」「ビニール手袋着用の禁止」「革靴使用の強要」「バスでの移動の強制」は、証拠上も認められない。
・Aさんの主張する、職場環境を改善する義務の懈怠があったと認めるに足る証拠もない。
以上から、Aさんの請求は認められないと判断されました。
ポイント
Aさんの主張や請求は認められなかったものの、裁判所が「合理的配慮に準ずる義務」を認めた点が注目されます。
判例から学ぶ、企業が取るべき3つの行動
この判例からは、企業が法的リスクを回避しながら、従業員とともに成長していくために取るべき行動が見えてきます。
従業員の特性を正確に把握する対話の場を設ける
「合理的配慮」は画一的なものではありません。
従業員一人ひとりの障がい特性、その日の体調、業務内容に応じて対応する必要があります。
定期的な面談や、いつでも相談できる窓口を設けるなど、建設的な対話を継続する仕組みを構築しましょう。
「できないこと」ではなく「能力の向上」に焦点を当てる
単に業務負担を軽減するだけでなく、「どうすればこの業務を遂行できるようになるか」をともに考える姿勢が大切です。
業務を細分化してステップを明確にしたり、スキルアップのための研修を提供したりと、本人の成長を支援する視点を持ってアプローチしましょう。
従業員間の相互理解を深める
障がいのある従業員への配慮は、現場の上司や同僚の理解なくしては成り立ちません。
社内研修や勉強会などを通じて、障がいへの正しい知識と、互いに支え合うことの重要性を共有することで、職場全体の心理的安全性が高まり、すべての従業員にとって働きやすい環境が生まれます。
まとめ
今回の判例は、合理的配慮が単なる制度上の義務ではなく、『企業と従業員の信頼関係』に基づくものであることを示しています。
障がい者雇用を成功させるには、従業員の声を丁寧に聴き、その人にとって本当に必要な支援は何かを共に考え、実行に移すことが不可欠です。
それは、法的リスクを回避するだけでなく、組織全体の連帯感を高め、企業の価値向上にもつながる重要な経営戦略となるでしょう。