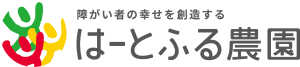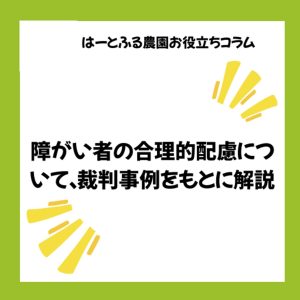従業員のメンタルヘルスを守り、生産性向上!効果的な対策とは
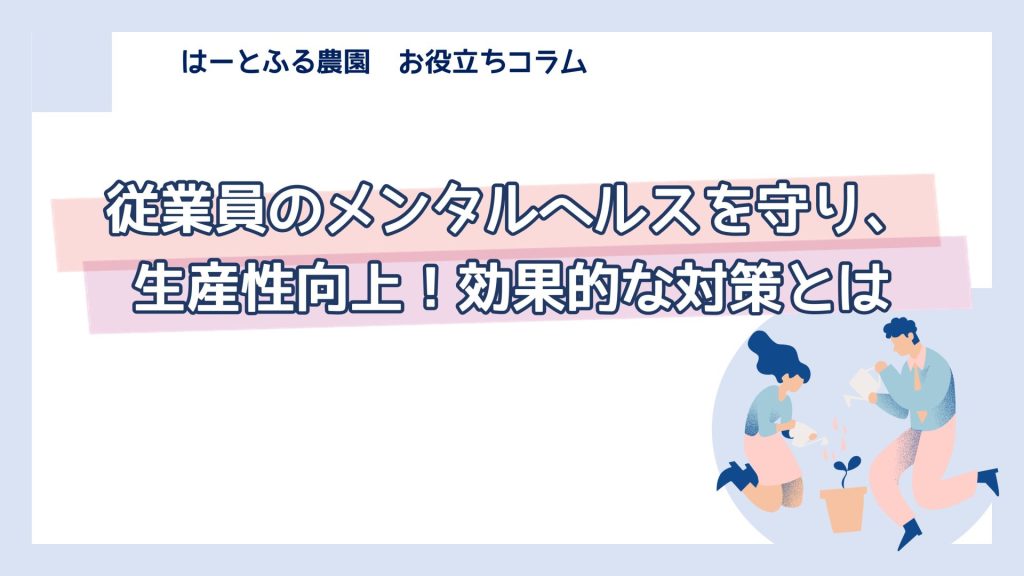
近年、働き方改革や職場環境の多様化により、従業員のメンタルヘルス対策の重要性がますます高まっています。
企業にとってメンタルヘルス対策は生産性や組織の持続可能性に直結する課題です。
心の不調がもたらす業務への影響や人材流出リスクなどへの対応が急務とされています。
そこでこの記事では、企業が取り組むべきメンタルヘルス対策のポイントや具体的な施策を多角的にご紹介します。
企業におけるメンタルヘルス対策の重要性
メンタルヘルスの不調は、従業員個人の健康問題にとどまらず、生産性低下や休職者・離職者の増加、訴訟問題、企業イメージの悪化など、企業にさまざまなリスクをもたらします。
また、近年日本では、人口減少・少子高齢化による労働力不足や医療費の増大などの理由から「健康経営」が注目されており、メンタルヘルス対策もその一環として位置づけられています。
こうした背景から、企業が積極的にメンタルヘルス対策に取り組むことで、従業員の幸福度向上だけでなく、企業の持続的な成長の実現が期待でき、重要な取り組みです。
企業が実施すべきメンタルヘルスケア施策
厚生労働省が公表している「職場における心の健康づくり」では、メンタルヘルスケアの基本的な考え方として「4つのケア」が提唱されています。
厚生労働省が提唱する「4つのケア」とは
厚生労働省が提唱する「4つのケア」とは、「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア(内部EAP)」「事業場外資源によるケア(外部EAP)」です。
①セルフケア
セルフケアとは、従業員一人ひとりがストレスについて理解し、自らのストレスに気づき、これに対処することです。
企業には、従業員がセルフケアを行うための知識や機会を提供することが求められます。
具体的には、
・ストレスに関する情報提供
・リラクゼーション技法の紹介
・ストレスマネジメント研修の実施
などが挙げられます。
なお、セルフケアの対象者には、管理監督者も含まれます。
②ラインによるケア
ラインによるケアとは、職場の管理監督者(上司)が、部下の心の健康状態に常に気を配り、不調の早期発見や職場環境の改善に努めることです。
管理監督者には、部下との日頃からのコミュニケーションを通じて、「いつもと違う」部下の変化に気づく役割や部下からの相談への対応、部下の職場復帰への支援が求められます。
企業は、管理監督者に対して、メンタルヘルスに関する研修を定期的に実施し、適切な知識と対応能力を養う機会を提供する必要があるでしょう。
③事業場内産業保健スタッフ等によるケア(内部EAP)
事業場内産業保健スタッフ等によるケアとは、人事部門や産業医、保健師、精神科医、公認心理師などの専門家が、従業員のメンタルヘルスに関する相談対応や、ラインケアへの助言、職場復帰支援などを行うことです。
事業場内にこれらの専門家を配置することは、専門的な視点からきめ細やかなサポートを提供することを可能にします。
④事業場外資源によるケア(外部EAP)
事業場外資源によるケアとは、社外の専門機関(医療機関、カウンセリング機関、EAPサービス提供機関など)と連携し、専門的な支援を受けることです。
具体的な支援内容としては、ネットワークを形成し、情報提供や助言を受けたり、ケアを受けたり、職場復帰におけるサポートを受けたりといったことが挙げられます。
これにより、社内では対応が難しい専門的な相談や治療、匿名性を求める従業員への対応が可能になります。
特に従業員規模の小さい企業では、外部EAPの活用が現実的かつ効果的な方法でしょう。
ストレスチェック制度の実施
ストレスチェック制度は、2015年12月に施行された労働安全衛生法改正により、常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられました。
単にストレス度を測るだけでなく、その結果を多角的に活用することで、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、職場環境の改善に繋げることを目的として作られました。
ストレスチェックを実施後、高ストレス者には、医師による面接指導を促し、早期のケアにつなげましょう。
面接指導の結果に基づき、就業上の措置を検討することも重要です。
また、ストレスチェックの結果を部署やチームごとに集計・分析し、どのような職場要因がストレスの原因となっているかを特定することも重要です。
たとえば、長時間労働が常態化している部署があれば、業務の見直しや人員配置の改善を検討します。集団分析の結果は、匿名性を保ちつつ、従業員にもフィードバックすることで、職場全体の改善意識を高めることができるでしょう。
メンタルヘルス研修と従業員への情報提供
メンタルヘルスに関する正しい知識の普及は、偏見をなくし、早期相談や適切な行動を促す上で不可欠です。
具体的には、次のような方法が挙げられます。
全従業員向け研修
ストレスの定義やメカニズム、ストレスへの対処法(セルフケア)、メンタルヘルス不調のサイン、相談窓口の利用方法など、基本的な知識を全従業員向けにわかりやすく提供しましょう。
Eラーニング形式も有効です。
管理職向け研修
部下のメンタルヘルス不調の早期発見や、その際の適切な声かけ、ハラスメント防止、休職・復職支援における管理職の役割、相談窓口へのつなぎ方など、実践的な内容に特化して行いましょう。
情報提供
社内報やポスター、イントラネットなどを活用し、メンタルヘルスに関する情報や相談窓口の案内を定期的に発信しましょう。
メンタルヘルスは特別なことではなく、誰もがなり得る状態であるという認識を共有することが重要です。
メンタル不調への対応フロー
従業員がメンタル不調に陥ってしまった場合は、迅速かつ適切に対応することで、その後の回復や再発防止につながります。
次のようなフローで適切に対処しましょう。
産業医との連携し、早期発見に努める
従業員の様子に変化が見られた際や、本人から不調の訴えがあった場合は、速やかに産業医と連携し、早期発見に努めます。状況に応じて、産業医面談を設定し、専門的な見地からのアセスメントと助言を仰ぎましょう。
なお、産業医との面談内容は、本人の同意なく第三者に開示してはなりません。
プライバシー保護を徹底することで、従業員は安心して相談できるようになります。
面談後、産業医に従業員の症状や業務への影響を評価してもらい、休職の必要性や期間について意見を受けましょう。
企業は、本人の意向も踏まえて総合的に判断します。
休職・復職時のフォロー体制を整備する
判断の結果、休職の必要があるとわかれば、休職に向けた手続きを行います。
休職期間中も、定期的に連絡を取り、従業員の状況を把握しましょう。
ただし、過度な干渉は避け、本人の回復を最優先に考えます。
必要に応じて、傷病手当金などの情報提供も行います。
また、復職する際は、産業医の意見に基づき、段階的な復職プログラム(試し出勤制度、リハビリ出勤など)を実施しましょう。
業務内容や勤務時間を調整し、段階的に職場復帰を進めます。
さらに、復職後の再発防止のため、業務内容の見直しや時短勤務、配置転換など、従業員の状況に合わせた職場環境の調整を検討しましょう。
再発防止について詳しくは、事項でお伝えします。
再発防止のために職場環境を改善する
再発防止のためには、職場環境を改善する必要があります。
具体的には、次のようなポイントが重要です。
原因究明と対策
メンタル不調の原因が職場環境にある場合は、その原因を特定し、具体的な改善策を講じましょう。
定期的なフォローアップ
たとえば、特定の部署で休職者が多発している場合、業務量や人間関係に問題がないか深く掘り下げて分析します。
復職後も、産業医や上司による定期的な面談を実施し、従業員の心身の状態を確認しましょう。
必要に応じて、産業医面談の再設定や外部EAPの利用を促します。
再発防止策の共有
メンタル不調からの復職経験がある従業員の事例(個人が特定できないかたち)があれば、それを参考に、企業全体として再発防止策を共有し、組織的な学びと改善につなげましょう。
従業員のメンタルヘルスケアのためのポイント
従業員のメンタルヘルスケアのための主なポイントは、次の5点です。
日常のコミュニケーションを活性化する
日常のコミュニケーションを活性化することで、従業員のメンタルの変化に一早く気づけたり、メンタルヘルスを良い状態でキープしたりすることにつながります。
たとえば、次の3つの施策がおすすめです。
定期的な1on1ミーティング
上司と部下が定期的に一対一で話し合う場を設けることで、業務上の課題だけでなく、部下の精神的な状態や悩みを把握しやすくなります。
ランチミーティングや社内イベント
業務外での交流を促進することで、従業員間の連帯感を高め、孤立を防ぎましょう。
オープンなフィードバック文化
従業員が安心して意見や悩みを共有できるような、風通しの良い職場環境を醸成します。
心理的安全性の高い職場づくりを行う
心理的安全性とは、組織の中で自分の意見や考えを安心して発言できる状態を指します。
心理的安全性が高い職場では、従業員は失敗を恐れずに挑戦し、建設的な議論が生まれるため、生産性向上にもつながります。
次のような工夫がポイントとなるでしょう。
リーダーの行動の変容
管理職者が率先して弱みを見せたり、間違いを認めたりすることで、部下も安心して発言できるような環境を作り出せます。
ポジティブなフィードバックを行う
挑戦や努力を認め、ポジティブなフィードバックを積極的に行うことで、従業員の自信と意欲を高められます。
対話の促進
オープンな対話を奨励した上で、異なる意見を尊重することで、多様な視点からの解決策が生まれる効果が期待できます。
ストレスチェックの結果を活用する
前述の通り、ストレスチェックは単なる義務ではなく、企業が従業員のメンタルヘルス状態を把握し、具体的な改善策を講じるための重要なツールとなります。
ストレスチェックを実行したら、結果をもとに、次のような施策に取り組みましょう。
集団分析結果の公開とディスカッション
匿名性を保ちながら、部署ごとの集団分析結果を従業員に共有し、改善点についてともに議論する場を設けましょう。
具体的な改善策の実施と効果測定
集団分析で明らかになった課題に対し、具体的な改善策(例:業務量の平準化、コミュニケーション促進策など)を実行し、その効果を定期的に測定・評価しましょう。
柔軟な働き方を導入し、職場環境を整備する
柔軟な働き方を導入することで、従業員のストレス軽減とワークライフバランスの向上につながり、ひいては企業の生産性向上が期待できます。
具体的には、次のような環境整備がポイントです。
テレワーク・リモートワークの推進
テレワーク・リモートワークを推進することで、通勤ストレスの軽減やプライベートとの両立など、従業員の柔軟な働き方を実現できます。
フレックスタイム制の導入
従業員が自身のライフスタイルに合わせて始業・終業時間を調整できることで、ストレスを軽減できるだけでなく、集中力向上も期待できます。
有給休暇の取得促進
従業員が気兼ねなく休暇を取得できるよう、取得しやすい雰囲気作りや、計画的な取得を促す仕組みを導入しましょう。
定期的にメンタルヘルス教育を実施する
メンタルヘルスに関する知識は日々更新され、また従業員の状況も変化するため、定期的な教育は不可欠です。
特に、次のような教育がおすすめです。
継続的な研修プログラムの実施
入社時だけでなく、定期的にメンタルヘルス研修を実施しましょう。
内容も、セルフケア、ラインケア、ハラスメント対策など、多角的なプログラムが重要です。
最新情報の提供
メンタルヘルスに関する最新の研究成果や、国の取り組み、企業の成功事例などを共有し、従業員の意識を高めましょう。
体験型学習の導入
ロールプレイングやグループワークなど、実践的な体験を通して、知識を深める機会を提供しましょう。
まとめ
従業員のメンタルヘルスを守り、生産性を向上させるためには、企業が多角的かつ継続的に取り組むことが不可欠です。
厚生労働省が提唱する「4つのケア」を軸に、ストレスチェックの適切な活用、ハラスメント対策を含む職場環境の整備、柔軟な働き方の導入、そして継続的なメンタルヘルス教育を実施しましょう。
従業員一人ひとりが心身ともに健康で、安心して働ける環境を整えることで、企業の競争力強化につながります。
ぜひ、この記事で紹介した対策を参考に、貴社の従業員のメンタルヘルスケアを推進し、より一層の生産性向上と企業価値の向上を目指しましょう。