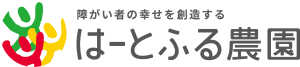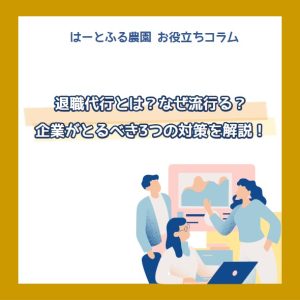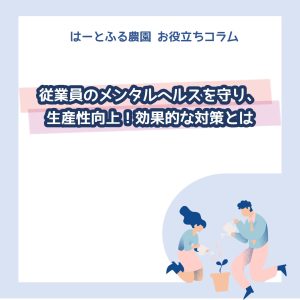2025年法改正で押さえるべき障がい者雇用関連の最新トピック
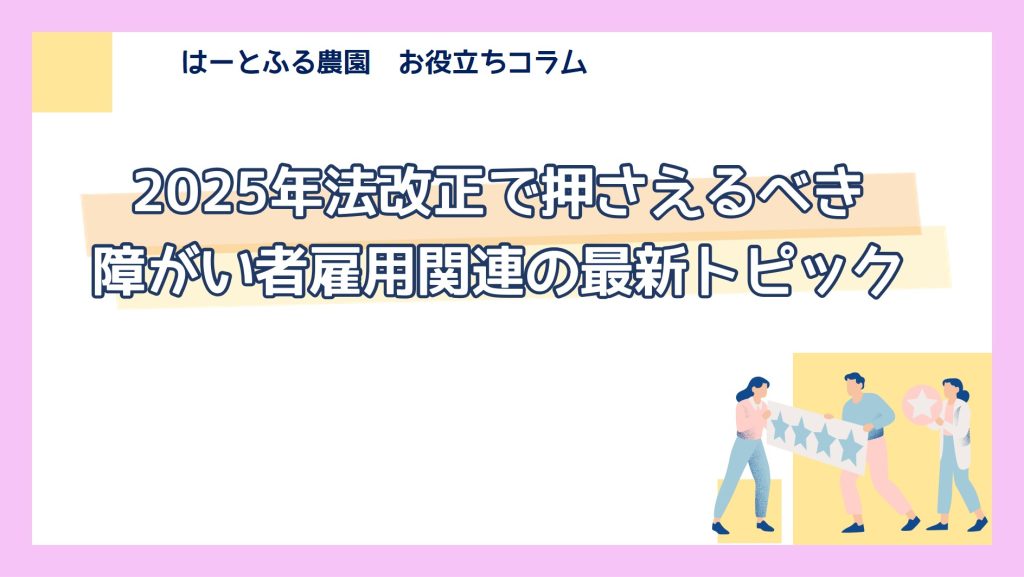
2025年4月、企業の障がい者雇用に関する法制度が変わります。
今回の法改正は、単なる制度上の更新にとどまらず、
「誰もが働きやすい職場環境づくり」に向けた社会全体の価値観の変化を反映した内容となっています。
しかし、「何がどう変わるのか」「自社はどう対応すべきか」を把握できていない人事部門や経営層の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、障がい者雇用に関する法律や制度の基本や、法令順守の重要性や制度利用のメリットについてわかりやすく解説するとともに、
2025年に施行される障がい者雇用関連の法改正のポイントをご紹介いたします。
障がい者雇用に関する法律・制度の一覧
2025年の法改正を確認する前に、障がい者雇用に関する法律・制度を押さえておきましょう。
障害者基本法
障害者基本法とは、障がいのある方々の自立と社会参加を促進し、全ての国民が個人として尊重され、地域社会において共生できる社会の実現を目指すための基本的な理念を定めた法律です。
障がい者施策全般の基本となる法律であり、障害の範囲の定義や、障がいのある方々の権利保障、差別の禁止などを定めています。
障害者雇用促進法
障害者雇用促進法とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の略称で、障がいのある方々の職業の安定を図ることを目的とした法律です。
障がい者の雇用義務(法定雇用率)や合理的配慮の提供、差別の禁止、障害者雇用納付金制度、助成金制度などが定められており、企業が障がいのある方々を雇用する上で遵守すべき具体的な規定が盛り込まれています。
障害者差別解消法
障害者差別解消法とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の略称です。
障害者基本法の基本的な理念に則り、障がいのある方々に対して不当な差別的取扱いをすることの禁止、および障がいのある人から社会生活を送る上で障壁となるものを取り除くために、合理的な配慮を提供することを義務付けています。
令和6(2024)年4月1日からは、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
障害者総合支援法
障害者総合支援法とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称です。制定時は「障害者自立支援法」の名称で、平成24(2012)年4月1日の改正で、現在の名称に改称されました。
障がいのある方々が地域社会で安心して暮らせるよう、障害保健福祉施策について定めた法律です。
就労支援も、この法律に基づいて提供されています。
各種助成金制度
障がい者雇用を促進するために、さまざまな助成金制度も用意されています。
障害者トライアル雇用奨励金
障害者トライアル雇用奨励金とは、厚生労働省とハローワークが管轄する助成金で、障がいのある方々を原則3ヵ月間試行雇用(トライアル雇用)する場合に支給される奨励金です。
トライアル雇用助成金には「一般トライアルコース」と「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」があり、後者が障がい者雇用の対象となっています。
職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金
障がいのある方々の職場適応を支援する専門家(ジョブコーチ)による支援を利用する場合に支給される助成金です。障がいのある方々の職場への定着を促進するために活用されます。
障害職場適応援助者助成金は、「訪問型職場適応援助者の助成金」と「企業在籍型職場適応援助者の助成金」に分かれており、障がいのある方々を雇用する企業が対象となるのは、後者です。
ジョブコーチを配置する場合の費用が一部助成されます。
金額は、中小企業かどうか、短時間労働者かどうかなど、条件によって異なります。
助成対象期間は最大6ヵ月間。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者や障がいのある方々、母子家庭の母など、就職が困難な方をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。
対象者別に、以下の8つのコースがあります。
・特定就職困難者コース
・生涯現役コース
・被災者雇用開発コース
・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
・三年以内既卒者等採用定着支援コース
・障害者初回雇用コース
・定雇用実現コース
・生活保護受給者等雇用開発コース
このうち、障がい者雇用に関わるのは、「特定就職困難者コース」「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」「障害者初回雇用コース」です。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者雇用納付金制度は、法定雇用率を達成していない企業から納付金を徴収し、法定雇用率を達成している企業や障がい者雇用に積極的に取り組む企業に対して助成金を支給する制度です。
施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合に助成金を受け取ることができます。
障がいのある方々の雇用の機会を確保し、雇用の水準を高めることを目的としています。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
障がいのある非正規雇用労働者を正社員として職場定着のための措置を実施した場合に活用できる可能性があります。
助成金については、下記の記事もご覧ください。
【関連記事】
障がい者雇用に利用できる助成金を活用しよう!~申請方法と活用事例~
障がい者雇用に関する法令順守の重要性
障がい者雇用に関する法令を遵守することは、企業にとって単なる義務ではなく、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で不可欠です。
法定雇用率の達成はもとより、合理的配慮の提供義務など、法令に定められた要件を満たさない場合、指導や勧告、さらには企業名の公表といった行政指導の対象となる可能性があります。
これは、企業のブランドイメージや信頼性に大きな打撃を与えかねません。
また、障がい者差別解消法の遵守は、ハラスメントや差別の防止にもつながり、全ての従業員にとって公平で働きやすい職場環境を築くための基盤となります。
法令を遵守し、積極的に障がい者雇用に取り組むことは、企業価値の向上にもつながるでしょう。
障がい者雇用に関する制度利用のメリット
障がい者雇用に関する各種制度を積極的に利用することで、以下のようなメリットが期待できます。
人件費・設備費の負担を軽減できる
各種助成金制度を活用することで、障がい者雇用にかかる人件費や職場環境整備のための設備費などの経済的負担を軽減することができます。
これにより、障がい者雇用のハードルが低くなり、より多くの企業が雇用に踏み出しやすくなります。
障がい者雇用がしやすくなり、労働力の多様化を図れる
助成金や専門家による支援を活用することで、障がい者雇用に関するノウハウがない企業でも安心して雇用を進めることができます。
障がい者雇用を実現した結果、企業内に多様な視点や能力がもたらされ、組織全体の活性化やイノベーションの創出につながる可能性を高められます。
また、企業の社会的評価向上にもつながります。
2025年法改正で押さえるべき障がい者雇用関連の最新トピック
2025年、「障害者雇用促進法 」の法改正によって日本の障がい者雇用を取り巻く環境は大きく変化します。
企業が押さえるべき主要な法改正ポイントは、「障がい者法定雇用率引き上げ(除外率の引き下げ)」です。
障がい者法定雇用に関して、令和7(2025)年4月1日から、特定の業種に設定されていた「除外率」が一律10ポイント引き下げられました。
これにより、障がいのある方々の雇用が難しいとされてきた業種でも、より多くの障がいのある方々を雇用する必要が出てきます。
また、2025年の改正ではありませんが、民間企業の障がい者法定雇用率が、令和6(2024)年4月に2.3%から2.5%へ引き上げられ、さらに令和8(2026)年7月には2.7%への引き上げが予定されています。
これに伴い、雇用義務の対象となる企業の規模も拡大します。
現在は従業員40人以上の企業に雇用義務がありますが、令和8(2026)年7月以降は37.5人以上の企業も対象となります。
なお、2024年4月より、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障がい者、重度身体障がい者、および重度知的障がい者も、雇用率の算定対象に含まれるようになりました(0.5人としてカウント)。
企業が今から取り組むべき対策
この法改正に対応し、障がい者雇用を成功させるために、企業は以下の対策を講じる必要があるでしょう。
障がいのある方々の採用・雇用戦略の見直し
自社の常用労働者数と障がい者雇用状況を正確に把握し、法定雇用率達成に向けたギャップを特定することが重要です。
除外率の引き下げや短時間労働者の算入を考慮し、必要な障がい者雇用数を再計算しましょう。
ハローワーク、転職サイト、就労移行支援事業所、特別支援学校など、障がい種別や働き方に応じた多様な採用ルートの開拓も不可欠です。
障がいのある方々が活躍できる業務の創出や、業務の細分化・職務設計を通じて、より多くの雇用機会を提供することも検討してください。
職場環境・業務体制の整備
合理的配慮の提供が義務化されていることを踏まえ、障がいのある方々の特性や状況に応じた職場環境の整備を進めましょう。
物理的なバリアフリー化はもちろん、業務マニュアルの視覚化、ITツールの活用、柔軟な勤務時間制度の導入なども有効です。
また、個別のニーズに応じた支援体制を構築し、必要に応じて業務内容や進め方を調整できる柔軟性も求められます。
社内理解促進と教育体制の構築
障がい者雇用は、一部の担当者だけでなく、組織全体で取り組むべき課題です。
障がいへの理解を深めるための社内研修や勉強会を実施し、全従業員が合理的配慮の重要性を認識することが不可欠です。
特に、障がいのある方々と直接関わる可能性のある現場スタッフに対しては、障がい特性に応じたコミュニケーション方法や支援スキルの習得を促す教育を徹底しましょう。
メンター制度の導入なども、障がいのある方々の定着を促進する上で有効です。
外部支援サービスの活用
自社だけで障がい者雇用の全てを担うのは難しい場合もあります。
その際は、外部の支援サービスを積極的に活用しましょう。
就労移行支援事業所や地域障害者職業センター、ハローワークなどの公的機関は、障がい者雇用の専門家として、求人開拓から採用、定着支援まで一貫したサポートを提供しています。
また、ジョブコーチ支援事業や障害者雇用相談援助事業なども活用し、専門家のアドバイスを受けながら雇用を進めることで、企業側の負担を軽減し、より効果的な障がい者雇用を実現できます。
たとえば、「はーとふる農園」は、農業を通した障がい者雇用サービスです。
障がいのある方の募集活動から、農園での就農訓練、ご紹介、面接のセッティング、雇用後の職場定着サポートまで、一貫してサポートいたします。
初期設備投資0円で始めることができ、リースではなくレンタルなので、お客様で資産計上をする必要もありません。
詳しくは、下記の公式サイトをご覧ください。
まとめ
2025年の法改正は、障がい者雇用を巡る企業の責任と機会を広げるものです。
企業にとって新たな挑戦となる一方で、多様な人材の活用による組織力強化、企業イメージ向上といったメリットももたらします。
これらの変更点を単なる義務と捉えるのではなく、企業文化の変革や持続可能な経営を実現するための契機として捉え、積極的かつ戦略的に障がい者雇用に取り組むことが、これからの企業経営において不可欠となるでしょう。