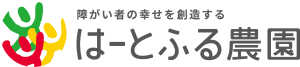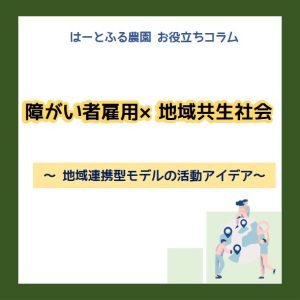退職代行とは?なぜ流行る?企業がとるべき3つの対策を解説!
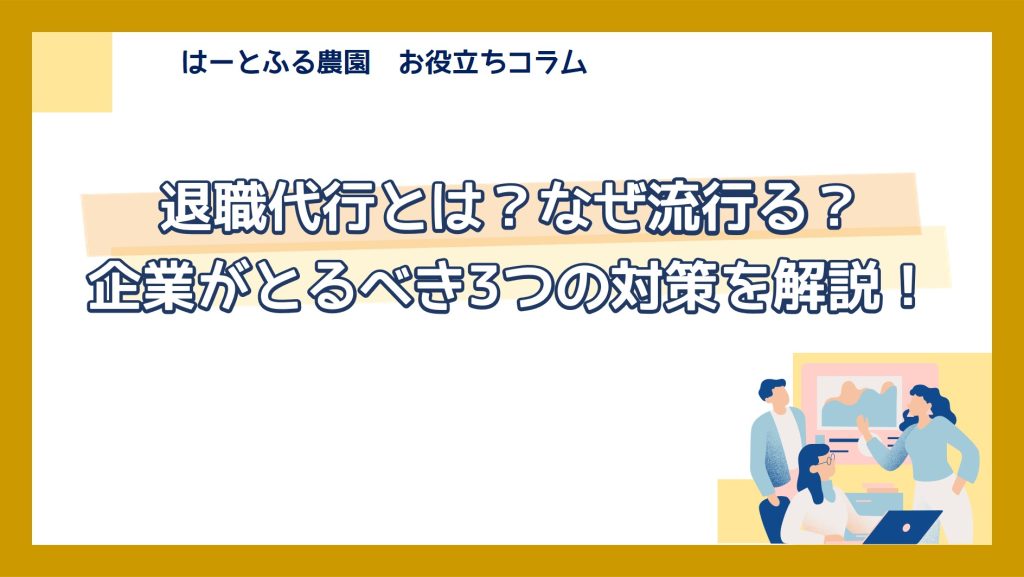
近年、若手社員を中心に「退職代行サービス」を利用して会社を辞めるケースが見られます。
企業にとっては、突然の退職通知や第三者からの連絡に戸惑いを感じることも少なくありません。
人手不足が深刻化する中での突然の人員離脱は、事業運営に大きな支障をきたす可能性もあります。
特に中堅・中小企業では、代替人材の確保も容易ではないため、現場の混乱を最小限に抑えるための対応が急務です。
この記事では、退職代行の現状や背景を整理した上で、企業として押さえておくべき基本対応と、
再発防止につなげるための3つの実践的な対策についてご紹介いたします。
退職代行とは?
退職代行とは、従業員本人に代わって、退職の意思表示や会社との連絡を代行するサービスのことです。
退職代行業者には、主に以下の2つのタイプが存在します。
・弁護士が運営するタイプ…法律の専門家である弁護士が、退職に関する交渉や手続きを代行します。
・民間企業が運営するタイプ…退職の意思を伝えることのみを代行し、会社との交渉は行いません。
どちらのタイプも、退職代行は労働者の「退職の自由」を背景としており、正社員であれば退職希望日の2週間前までに会社に申し出れば、会社の承諾がなくても退職できるという民法上の規定に基づいています。
なお、株式会社東京商工リサーチのWebサイトによれば、2024年1月~2025年6月までの間に、退職代行による退職を経験した企業は7.2%で、大企業においては15.7%にのぼるといいます。
退職代行サービスの利用年代は20代が約6割と最多である一方で50代以上も約1割いたとの結果が出ています。
出典:「退職代行」による退職、大企業の15.7%が経験 利用年代は20代が約6割、50代以上も約1割(株式会社東京商工リサーチ)
退職代行が流行る3つの理由
退職代行サービスは、かつてはあまり知られていない存在でしたが、ここ数年で急速に認知度が高まっています。
企業としては、なぜ従業員がこうしたサービスを使ってまで退職したいのか、その背景を理解することが、適切な対応や防止策を講じる上で重要です。
ここでは、退職代行が流行する主な3つの理由を整理してご紹介します。
上司や会社と直接話す心理的負担が大きいから
多くの退職代行利用者が利用する理由が、「直接、言い出せない」という心理的ハードルです。
特に若手社員の中には、上司との関係が希薄だったり、過度なプレッシャーを受けていたりすることで、退職の意向を伝えることに大きなストレスを感じてしまうケースがあります。
退職を切り出した際に、引き止められたり、説得されたりすることへの不安も利用動機となっているようです。
ブラック企業やハラスメント環境で退職の意思を伝えることすら危険だから
近年、SNSなどで職場環境の“ブラック化”やパワハラ・モラハラ被害が可視化されるようになりました。
こうした職場においては、上司に退職の意思を伝えることすら危険と感じるケースもあり、第三者である退職代行業者の存在が「安全な退職手段」として注目されています。
自分の意思が通らない、退職届を受け取ってもらえないなどのトラブルを避けるためにも、専門業者のサポートを求める流れが広がっているといえます。
サービス利用が手軽かつ低価格化しているから
現在では、LINEやWebフォームだけで退職代行を依頼できる手軽なサービスが増え、費用も2~3万円程度が主流となっています。
この手軽さと費用の手頃さが、若年層を中心に利用を後押ししています。また、弁護士監修や労働組合による対応など、法的リスクに配慮したサービスも登場しており、利用者にとって安心感のある選択肢となっています。
退職代行を使われた場合の具体的な対応方法
退職代行サービスから従業員の退職の連絡を受けた際、企業側は冷静かつ適切な対応を求められます。
次のようなフローで対応すると良いでしょう。
代行業者の身元確認
退職代行業者から連絡があった場合、まずは相手の身元を正確に確認しましょう。
具体的には、以下の3点を確認します。
・会社名と担当者名…連絡してきた業者の正式名称と担当者名を確認します。
・連絡先…後日連絡が取れる電話番号やメールアドレスを聞いておきましょう。
・所属…弁護士資格を持つ業者か、または非弁行為を行わない民間企業かを確認します。弁護士法に抵触しない業者であるかを見極めることが重要です。
退職意思の確認と記録
次に、退職代行業者を通して伝えられた退職意思が、従業員本人のものであることを確認する必要があります。
本人への確認
退職代行業者に「本人の退職意思を直接、確認したい」旨を伝えましょう。
直接、連絡が取れない場合は、メールや書面で意思確認を行うことも検討します。
退職日の調整
退職代行業者から伝えられた希望退職日を確認します。
就業規則に則り、退職日の調整が必要な場合はその旨を伝えます。
この一連のやり取りは、後々のトラブルを避けるためにすべて記録しておくことが重要です。
必要書類の準備と手続き
退職が確定したら、企業側は法律に基づき、以下の手続きを進めます。
・離職票や雇用保険被保険者証の準備…従業員が次の転職先で必要となる書類を速やかに準備します。
・源泉徴収票の発行…法律で定められた期間内に、従業員に交付します。
・社会保険の手続き…健康保険証の回収や、社会保険の資格喪失手続きを行います。
これらの手続きは、退職代行業者ではなく、従業員本人またはその家族と直接やり取りを行うことが原則となります。
退職代行時代に企業がとるべき3つの対策
退職代行の利用が社会的な選択肢の一つとして定着しつつある現代において、企業は受け身の姿勢から脱却し、能動的な対策を講じることが重要です。
ここでは、退職代行の根本的な原因に対処し、従業員のエンゲージメントを高めるための3つの対策を解説します。
従業員の声に耳を傾ける「心理的安全性」の確保
「退職代行が流行る3つの理由」でもお伝えしたように、従業員が退職代行という第三者を介さなければならない背景には、「会社や上司に直接退職を伝えられない」という心理的な障壁があると考えられます。
この障壁を取り除くためには、組織の「心理的安全性」を高めることが不可欠です。
たとえば、次のような取り組みが考えられます。
1on1ミーティングの定期的な実施
業務の進捗だけでなく、従業員一人ひとりのキャリアに対する考えや、仕事に対するモチベーションの変化などを丁寧にヒアリングする場を設けます。
匿名での意見収集
従業員が本音を話しやすいように、社内アンケートや意見箱を匿名で設置し、定期的に意見を収集することも有効です。
安心して話せる環境作り
上司が部下の意見を否定せず、耳を傾ける姿勢を示すことで、「何を言っても大丈夫」という信頼関係を築きます。
こうした取り組みを通じて、従業員が抱える不満や悩みを早期に察知し、解決に向けた対話を促すことができるでしょう。
マネジメント層の意識改革
退職代行が利用される一因として、マネジメント層と従業員間のコミュニケーション不足や、ハラスメント、過度なプレッシャーなども挙げられます。
この問題を解決するには、マネジメント層の意識と行動を根本から見直す必要があります。
具体的には、次のような取り組みがおすすめです。
ハラスメント研修の義務化
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントの定義を再確認し、従業員に精神的な苦痛を与える言動を根絶するための研修を定期的に実施します。
フィードバック文化の醸成
一方的な指示ではなく、従業員の成長を促すための建設的なフィードバックを日常的に行います。これにより、従業員は自身の貢献を実感しやすくなります。
リーダーシップ研修の実施
部下のエンゲージメントを高めるための傾聴スキルや、コーチングスキルを学ぶ機会を提供し、マネジメント層全体の質を向上させます。
マネジメント層が率先して良好な人間関係を構築することで、従業員は「この会社で働き続けたい」と前向きな気持ちを抱きやすくなります。
スムーズな退職プロセスの構築
退職代行は、従業員が退職手続きの煩雑さや、上司からの引き止めにストレスを感じる場合に利用されることもあります。
そこで、退職プロセスをシンプルで透明性の高いものにすることで、従業員は安心して退職を決断できるようになります。
たとえば、次のような施策が考えられます。
就業規則の明文化と周知
退職を希望する場合の手順や、必要となる書類などを就業規則に明確に記載し、全従業員がいつでも確認できるようにしておきましょう。
退職手続きのオンライン化
書類提出のオンライン化や、電子署名の導入により、退職手続きの物理的・精神的な負担を軽減することも有効です。
専門部署の設置
人事部門など、退職に関する手続きを一括して担う専門の部署を設けることで、従業員は退職の相談をしやすい環境が整います。
まとめ
退職代行の利用があった場合は、企業と従業員の関係性を見直す良い機会です。
企業の対応は、退職代行への対処という一時的なものにとどまらず、「従業員が働きやすい環境をどう構築するか」という根本的な問いに対する答えを探すことにほかなりません。
心理的安全性を確保し、マネジメント層の意識を改革し、そして退職プロセスを改善することで、従業員一人ひとりが尊重されていると感じる文化を醸成できます。
これがひいては、従業員のエンゲージメントが向上し、結果として組織全体の生産性や離職率の改善にもつながっていくでしょう。