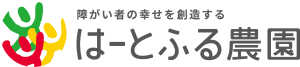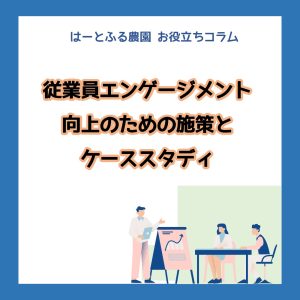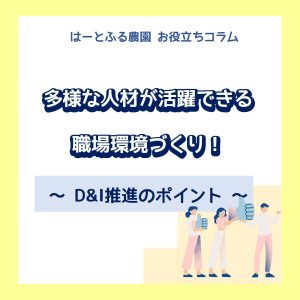労務トラブルを防ぐ!就業規則作成・改定のポイント
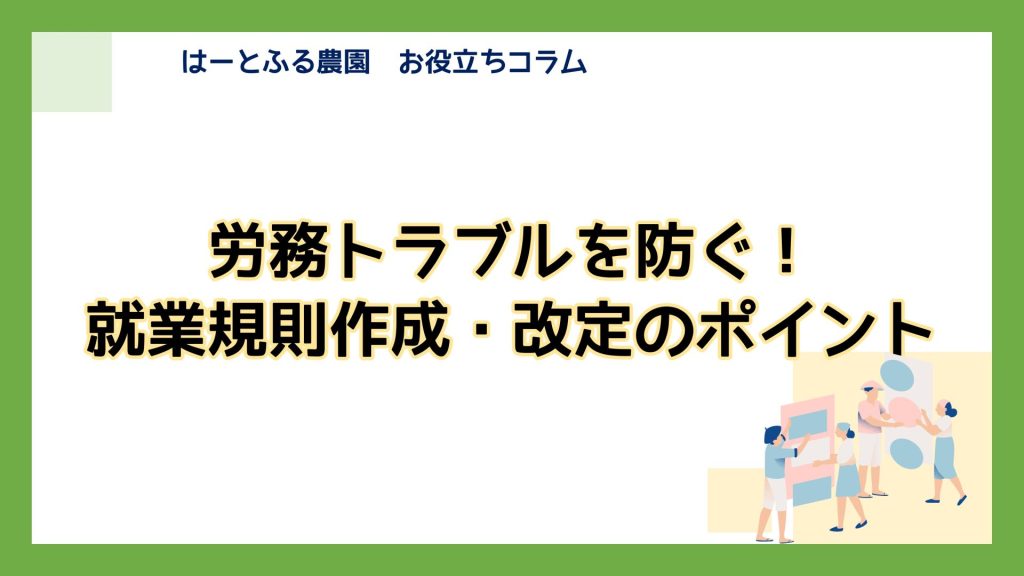
企業にとって、従業員との間で生じる労務トラブルは業務に大きな影響を与える要因の一つです。
特に、就業規則が不備であったり、現状に即していなかったりする場合、トラブルの原因になりかねません。
近年では、労働関連法令の頻繁な改正や、多様な働き方への対応が求められる中、
企業規模に関わらず、就業規則の作成・改定は非常に重要な課題となっています。
本記事では、労務トラブルを未然に防ぐために必要な就業規則の基礎知識、作成・改定の手順、注意点について解説いたします。
就業規則とは?
就業規則とは、従業員が安心して働ける職場環境を整備し、企業と従業員双方の権利義務を明確にするために作成する文書のことです。
具体的には、労働条件や職場でのルール、手続きなどを事前に明文化することで、認識のズレによるトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
就業規則を作成する目的
就業規則を作成する目的は、会社と従業員双方にとってより良い労働環境を築き、認識のズレをなくして円滑な企業運営を実現することにあります。
大きく分けて以下の3つの目的が挙げられます。
● 労使関係の明確化と安定化
就業規則によって、労働条件や服務規律など、会社と従業員の間の重要なルールを明文化します。
これにより、双方における権利義務関係を明確化し、誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
たとえば、賃金、労働時間、休日、休暇、懲戒に関する事項などを明確に定めることで、労使間の信頼関係を構築し、安定した雇用関係を築く基盤となります。
公平で透明性の高い人事労務管理を実現することで、従業員のモチベーション向上にもつながります。
● 企業秩序の維持と円滑な業務運営
就業規則は、企業理念や行動規範を反映し、従業員が遵守すべきルールを定めることで、企業秩序の維持にも貢献します。
たとえば、情報管理や服務規律、安全衛生に関する規則を設けることで、企業全体の規律を高め、円滑な業務運営を促進することができます。
また、コンプライアンス遵守の観点からも、就業規則は重要な役割を担います。
適切な規則を設けることで、法令違反や不正行為のリスクを低減し、健全な企業経営を実現できます。
● 従業員の権利保護
就業規則は、単に会社だけのルールではなく、労働基準法などの法令に則って作成する必要があります。
これにより、従業員の権利を不当に制限することなく、最低限の労働条件を保障するための重要な役割を果たすのです。
就業規則には、労働基準法で定められた事項を記載する義務があり、仮に法令に違反する内容が記載されていたとしても、その部分は無効となります。
このように、就業規則は、従業員の権利を守るセーフティネットとしての機能も担っています。
労働基準法における就業規則の扱い
就業規則は、労働基準法第89条において定められています。
● 就業規則が必要な企業の条件
就業規則の作成義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられています。
ここでいう「労働者」には、正社員だけでなく、契約社員やパートタイマーも含まれます。
したがって、企業規模にかかわらず、対象人数を超えた時点で速やかに就業規則を作成・届出しなければなりません。
さらに、複数の事業所があり、それぞれで就業規則が異なる場合には、それぞれの事業所ごとに就業規則の届出が必要になる点にも注意が必要です。
● 記載が義務付けられる項目
就業規則に記載する項目には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります。
絶対的必要記載事項は、以下の3項目です。
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
一方、相対的必要記載事項は、以下の8項目です。
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
就業規則の作成・改定が必要なるタイミング
まず、就業規則を作成するタイミングは、「就業規則が必要な企業の条件 」でお伝えした通り、労働基準法で常時10人以上の労働者を使用する事業に義務づけられているため、被雇用者が10人になる時です。
ただ、事業拡大を予定している場合は、もう少し早い段階で作成すると良いでしょう。被雇用者が10人未満であっても、就業規則を作成することで労働条件や手続きを明確にすることで、従業員との関係性をスムーズにする効果が期待できます。
就業規則を改定するタイミングについては、次の3つが考えられます。
法令改正に対応する場合
就業規則は、労働基準法第92条によって、法令や労働協約に反してはならないと定められています。
そして、労働関連法令は、時代の変化や社会課題に応じて頻繁に改正されています。
たとえば、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化といった新たなルールが加わりました。
これらの法改正に対応しないまま就業規則を放置していると、法令違反となり、企業側に行政指導や是正勧告が入るリスクが高まります。
改定後は、速やかに労働基準監督署への届け出と、従業員への周知徹底を行いましょう。
社内制度の変更時
企業の経営方針や組織体制が変わると、評価制度、給与体系、福利厚生制度なども見直しが必要になる場合があります。
このような社内制度の変更が発生した際にも、就業規則の改定が必要です。
たとえば、テレワークやフレックスタイム制の導入、定年延長制度の見直し、育児・介護休業制度の拡充といった施策を導入する場合、従業員とのトラブル防止や制度の適切な運用のために、あらかじめ就業規則に明記しておくことが重要です。
また、制度変更に伴い従業員に不利益が生じる場合には、合理的な理由を示した上で慎重な説明と合意形成を図ることが求められます。
労務トラブルの発生後
万が一、労務トラブルが発生した場合にも、就業規則の見直しが必要になるでしょう。
たとえば、解雇や懲戒処分に関して明確な基準が定められていなかったために争いが起こったケースや、労働時間管理が不十分だったことによる未払い残業代請求訴訟などが該当します。
トラブルを受けて実態と規則のずれを認識した場合は、速やかに規則を現実に即した内容に修正し、再発防止に努めることが重要です。
就業規則を放置すると、次回以降も同様の問題が繰り返されるリスクが高まるため、トラブルを機に積極的な見直しと改定を行うべきです。
就業規則作成・改定の手順
就業規則を作成・改定する際は、単に文書を作るだけでは不十分です。
法令遵守はもちろん、実態に即した内容を整理し、労使の信頼関係を築くためにも、次の手順を押さえて進めましょう。
事前準備
まずは、作成・改定の目的と範囲を明確にすることから始めましょう。
たとえば、「テレワーク制度の導入に伴う改定」や「法改正への対応」など、今回の見直し対象を具体的に定義しておくと、その後の作業がスムーズになります。
さらに、関係部署(人事部門、法務部門、経営層など)との事前すり合わせも重要です。
多角的な視点を取り入れることで、現場運用に適した就業規則が作成できるようになります。
現行規則の見直し
次に、改定を行う場合は、現行の就業規則の内容を精査しましょう。
現在の規則と実際の運用にズレがないか、法改正に対応できているか、表現にあいまいな部分はないかをチェックします。
特に、過去に労務トラブルが発生した項目や、従業員から意見が出た部分は重点的に見直すべきです。
必要に応じて、他社の就業規則や最新の法令解説を参考にするのも有効でしょう。
条文の設計
見直しポイントが整理できたら、条文の設計作業に移ります。
ここでは、労働基準法に基づき、必要記載事項を過不足なく盛り込むことが求められます。
記載事項については、「記載が義務付けられる項目 」をご参照ください。
また、条文の表現はできる限り具体的かつ明確にすることが重要です。
あいまいな表現は後のトラブルの火種になりかねないため、曖昧さを排除し、誰が読んでもわかる内容を目指しましょう。
意見書の作成
新たな就業規則案が完成したら、従業員代表から意見を聴取し、その内容を記載した「意見書」を作成します。
この意見書は、たとえ反対意見であったとしても、就業規則の届出に必要な書類です。
意見聴取の際には、なぜこの改定が必要なのか、どのような影響があるのかを丁寧に説明し、従業員の理解を得るよう努めましょう。
そのような透明性の高いコミュニケーションが、後の混乱防止につながります。
労基署への届け出
意見書を添付した上で、所轄の労働基準監督署に就業規則変更届を提出します。
提出時には、就業規則本体、就業規則変更届、意見書の3点セットが必要です。
社内周知
最後に、改定後の就業規則を従業員に周知徹底しましょう。
労働基準法第106条では、就業規則は「常時各作業場の見やすい場所に掲示」したり備え付ける、または「書面交付」や「電子データでの提供」など、確実に閲覧できる状態にしておくことが義務付けられています。
周知を怠った場合、仮に労基署への届け出が完了していても、効力を持たないと判断されるリスクがあるため、十分注意が必要です。
就業規則を作成・改定する際の注意点
作成・改定時に特に注意すべきポイントについて、ご紹介します。
従業員に不利益を与える変更の扱いに注意する条文の設計
就業規則を変更する際に、従業員にとって不利益となる内容(例:賃金引き下げ、手当廃止、休暇取得条件の厳格化など)が含まれる場合は、特に慎重な対応が求められます。
労働基準法自体では直接的な規定はありませんが、関連する「労働契約法」で明確に定められています。
労働契約法第9条では、従業員の同意なしに不利益な変更を一方的に行うことを原則として禁止しています。
ただし、「合理的な理由」が認められれば、一定条件のもとで就業規則変更が有効になる場合もあります。
合理性の判断ポイントには、変更の必要性、内容の相当性、従業員への影響度、代替措置の有無などが含まれます。
変更を進める際には、事前に十分な説明と協議を行い、できるだけ従業員の理解を得ることが重要です。
労働協約と整合性を取る
就業規則の内容が、既存の労働協約(労働組合との取り決め)と矛盾していないかも必ず確認する必要があります。
労働協約は法律に近い効力を持つため、協約に反する就業規則の変更は無効となる恐れがあります。
たとえば、労働協約で特定の賃金体系が定められている場合、それと異なる内容を就業規則に盛り込んでも優先されるのは労働協約側です。
そのため、改定前には労働組合との協議を経て、整合性の取れた内容に修正することが不可欠です。
記載内容と実態の乖離を防ぐ
就業規則には、実態に即した運用可能な内容を記載する必要があります。
書面上は立派でも、現場運用に無理がある内容では、トラブルやコンプライアンス違反を招くおそれがあります。
たとえば、休憩時間の取り方、時間外労働の許可手続き、休暇申請の流れなど、日常業務に直結するルールは、現場運用と矛盾がないか事前に検証することが大切です。
また、就業規則の改定後も定期的に見直しを行い、実態とのずれが生じていないかチェックする仕組みを作っておくと安心です。
保管用の変更届は5年間の保存が必要
労働基準法施行規則により、就業規則変更届は5年間保存する義務があります。
適切な保存管理を怠ると、万一の際に不利な立場に置かれるリスクがあるため、労務管理体制の一環として厳格に管理しましょう。
まとめ
就業規則は、企業運営の根幹を支える重要な規程であり、従業員との信頼関係を築くためにも欠かせない存在です。
特に、労働関連法令の改正や働き方の多様化が進む中で、就業規則の作成・改定は単なる形式的な作業ではなく、企業のリスクマネジメントと成長戦略の一環として捉える必要があります。
本記事でご紹介したように、就業規則の作成・改定には、法令順守はもちろん、現場運用との整合性や従業員への影響を慎重に考慮することが求められます。
また、労務トラブルを未然に防ぐためには、適切な事前準備、従業員代表との協議、社内周知の徹底が不可欠です。
特に注意したいのは、不利益変更時の合理性確保や、労働協約との整合性、記載内容と現場実態との乖離防止です。
さらに、届け出後も5年間の書類保存義務がある点も忘れてはなりません。
安定した職場環境を築き、企業価値を高めるためにも、定期的な就業規則の見直しと、時代に即した柔軟な対応を心がけましょう。
今後の労働環境の変化にも備え、万全な体制で労務管理に取り組んでいきたいところです。