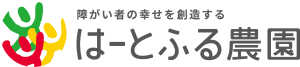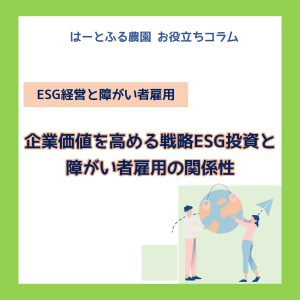障がい者雇用の壁を乗り越える! ~課題と解決策~
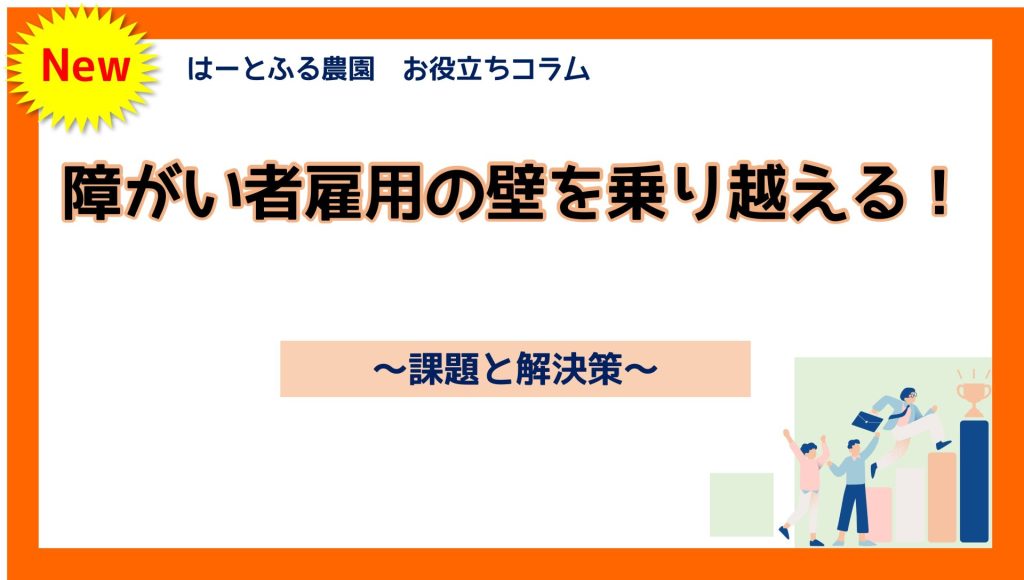
企業の障がい者雇用に関して、法定雇用率の引き上げや合理的配慮の提供義務化など、法制度の整備が進む一方で、
企業現場では依然としてさまざまな問題が浮き彫りになっています。
当然のことながら、法制度の整備だけでは障がい者雇用は十分に進展しません。
企業側には、障がい者を「雇用しなければならない」という義務感ではなく、「ともに働く仲間」として受け入れる意識改革が必要です。
また、合理的配慮についても、企業規模や業種によって提供可能な内容に差が生じる可能性があり、
実効性を確保するための施策が求められています。
本記事では、「障がい者雇用の壁を乗り越える!」をテーマに、
企業が抱える具体的な課題と、それを解決するための実践的な施策をご紹介いたします。
障がい者雇用における課題と解決策
まず、障がい者雇用において、よくある4つの課題を見てみましょう。
障がい者の採用・定着のハードルが高い
多くの企業が直面している代表的な課題の一つが、障がい者の採用や定着率です。
2024年度現在、民間企業に課されている障がい者の法定雇用率は2.5%(従業員数40名以上が対象)に引き上げられました。
たとえば40名規模の企業では対象者数が1名と少ないにもかかわらず、その1名の採用と定着が困難であるという声が多く聞かれます。
法定雇用率未達成により「障害者雇用納付金制度」への納付対象となることに加え、企業名の公表に対する懸念や、対外的なコンプライアンスの観点からのプレッシャーも、企業担当者の負担となっています。
法定雇用率の達成については、「障がい者雇用のはじめの一歩 ~基礎知識とメリット、押さえるべきポイント~(https://heartfulnouen.com/column/column01-2/)」もご覧ください。
● 解決策
まず着手したいのは「採用チャネルの多様化」と「外部支援機関との連携」です。
ハローワークだけでなく、障がい者雇用に特化した就職支援サービスや、就労移行支援事業所、特例子会社などとのネットワーク形成が効果的でしょう。
さらに、在宅勤務や短時間勤務といった柔軟な雇用形態の導入も、採用可能性を広げる一助になります。
適切な業務の切り出しが難しい
採用した障がい者に「何を任せたら良いのかわからない」と悩む企業も少なくありません。
業務の整理や障がい特性への理解が不十分な場合、障がいのある従業員に配慮を欠いた業務の割り振りをしてしまい、ストレスやトラブルを引き起こす恐れもあります。
特に中小企業では、業務が属人化していることが多く、明確に「切り出せる業務」を見極めることが難しいといえます。
障がい特性については「それぞれの個性を知る ~障がい特性と向いている仕事内容~(https://heartfulnouen.com/column/column02/)」もご覧ください。
● 解決策
まずは業務を「見える化」することが出発点です。社内の業務フローを棚卸しし、障がい者に向いた業務の特徴である「定型的」「反復的」「手順が明確」なものを抽出してみましょう。
たとえば、書類作成(見積書、契約書など)、発注管理、社内報の作成、などが該当します。
また、可能であればジョブコーチ(職場適応援助者)や障がい者雇用アドバイザーなど、専門家によるアセスメントを受けることで、適正な業務設計とマッチングが可能になります。
職場環境・人間関係への配慮が難しい
障がいのある従業員を迎えるにあたって、多くの現場担当者が感じるのが「どう接すれば良いのかわからない」という不安です。
特に精神障がいや発達障がいのある方の場合、外見から特性がわかりづらいため、周囲との摩擦や孤立を招くこともあります。
社内全体の理解が進んでいないまま採用を進めてしまうと、障がいのある従業員本人だけでなく、職場の他メンバーにもストレスを与えかねません。
● 解決策
最も効果的なのは、採用前からの「社内啓発」です。
障がい特性や配慮事項について、経営層から現場リーダー層までが共通認識を持てるように、外部講師による研修や、簡易なガイドブックの配布などを実施しましょう。
また、配属後には定期的なフォロー面談や、匿名で相談できる窓口を設けることで、早期に職場内の課題を可視化・改善する体制を整えることも大切です。
障がいごとの特性については「それぞれの個性を知る ~障がい特性と向いている仕事内容~(https://heartfulnouen.com/column/column02/)」もご覧ください。
採用後の長期的な定着が難しい
採用時点での課題に比べて、見過ごされがちなのが「支援体制」です。
入社後すぐの離職は、企業・本人ともに大きな損失となります。
特に中小企業では、人事部門と現場の連携が弱く、支援体制が十分に機能しないまま、本人の不安が蓄積してしまうケースが見られます。
● 解決策
職場定着のポイントは、「中長期的な雇用を見据えた支援体制の構築」と「外部支援機関による定着支援」にあります。
人事部門だけでなく、直属の上司や現場担当者との連携を強化し、役割分担を明確化しましょう。
また、支援体制の構築の具体的な内容として、支援記録表や業務日誌、定期的に面談の実施により、仕事や人間関係に関する悩みを聞き取る仕組みを整えましょう。
上記のような支援体制を構築し、さらに外部支援機関の定着支援を上手く連携させることで、より手厚いサポート体制を実現できます。
障がい者雇用を支援する外部リソースの活用
記ですでに触れた箇所もありますが、障がい者雇用にまつわる課題解決のためには、自社のリソースのみでなく、外部リソースをうまく活用することがポイントになります。
ここでは、具体的に活用すべき3つのリソースをご紹介します。
助成金制度の活用
厚生労働省をはじめとする行政では、障がい者の雇用を促進するための助成金制度を複数提供しています。
代表的な制度としては以下のようなものがあります。
・特定求職者雇用開発助成金
障がい者などを新たに雇い入れた企業に対して一定の助成金が支給されます。
対象は精神・知的・身体障がい者すべてに対応。
・障害者トライアル雇用助成金
雇用前に試用期間を設けてマッチングの可否を見極めることができる制度で、一定期間の雇用に対して助成金が支給されます。
・障がい者職場適応援助者助成金
障がい者が職場で適応しやすくなるように支援する「職場適応援助者(ジョブコーチ)」を配置する企業に支給される助成金です。
これらの制度は、企業側の雇用リスクを軽減し、継続的な支援体制をつくるきっかけにもなります。制度の要件や支給額は年度ごとに更新されるため、厚生労働省やハローワークの最新情報を定期的に確認しましょう。
助成金制度については、「障がい者雇用に利用できる助成金を活用しよう!~申請方法と活用事例~(https://heartfulnouen.com/column/column04/)」もご覧ください。
地域の「障害者就業・生活支援センター」との連携
各都道府県に設置されている「障害者就業・生活支援センター」は、障がい者の職業生活と日常生活を一体的に支援する機関です。
障がい者本人の支援にとどまらず、企業側への相談・アドバイスや職場定着のフォローなど、採用から定着までを支える幅広い支援が期待できます。
人事部門だけでなく、配属先のマネージャーとも連携しながら、「障害者就業・生活支援センター」の知見を活かすことで、現場での混乱やトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所との関係構築
就労移行支援事業所では、障がいのある方が一般企業への就職を希望する際に、就職に必要な知識やスキルを身につけたり、就職活動のサポートを受けたりすることができる福祉サービスを提供しています。
一方、就労継続支援A型・B型事業所一般企業への就職が難しい障がいのある方が働くための福祉サービス事業所です。
A型は雇用契約を結んで働く形態、B型はより支援度の高い非雇用型の作業が中心です。
企業側がこれらの事業所と連携することで、以下のような活用方法が考えられます。
- 業務の一部委託
- 職場実習の受け入れ
- 障がい者雇用のトレーニングの場を提供する
単なる業務委託先としてだけでなく、長期的なパートナーとして関係を築くことが、障がい者雇用の質を高める重要な要素になるでしょう。
「はーとふる農園」が解決できる課題
ここまで、障がい者雇用における課題解決のための方法やポイントをご紹介してきました。
ただ、一つひとつを解消させるために十分な手間暇をかけて取り組むことは、リソースの少ない中小企業にとって、簡単なことではありません。
そこでご提案したいのが、「はーとふる農園」のご利用です。
「はーとふる農園」は、企業が障がい者雇用で抱えるさまざまな課題を簡単に解消できるレンタル農園です。
初期投資0円で始められる
「はーとふる農園」では、障がい者雇用を希望する企業様に、一部区画をご利用いただきます。
さらに、当社から、実習を修了し、さらに就農を希望する障がいのある方をご紹介します。
必要な費用は月々の施設利用料に含まれておりますので、ご利用企業様に初期費用がかかりません。
体験実習を修了した障がいのある方をご紹介
「はーとふる農園」のご利用企業様には、実際の職場環境下で一定期間の就農体験実習を修了した障がいのある方をご紹介させていただきます。
そのため、雇用後の業務内容とのミスマッチが少なく、職場定着につながりやすいのが特徴です。
さらに、企業様には、雇用された障がいのある方を「はーとふる農園」に配属していただくしくみとなっており、法定雇用率の達成に大きくつながります。
障がい特性に合った業務をご用意
配属いただいた障がいのある方は、それぞれの専門的なスタッフによるサポートの下で「はーとふる農園」で農業に従事します。
障がいのある方にとって農業は医学的にも適しているとされており、「はーとふる農園」では、種まきから収穫、誰かに食べてもらう喜びまでを通じて、やりがいや自信につながる環境づくりに取り組んでいます。
また、郊外にお住まいで都心まで通勤が難しいといった悩みを抱える障がいのある方にとって、近場で職場の見つかる「はーとふる農園」は、通勤しやすい職場だといえます。
障がい者対応のエキスパートを全農園に配置
「はーとふる農園」では、ワークサポーターと呼ばれる障がい福祉のエキスパートや農業技術指導員を全農園に配置しています。
また、全スタッフには、独自の障がい者対応教育を実施しております。
このような障がい者対応のエキスパートが、障がいのある方をサポートするため、職場定着が期待できます。
実際に、はーとふる農園開園以来、定着率は約90%以上と高い数値を誇ります。※2025年4月末現在
まとめ
障がい者雇用における課題に対しては、まず社内の意識醸成と制度理解を深めることが第一歩です。
そのうえで、社内リソースの見直しや業務の整理、柔軟な雇用形態の検討、さらに外部の支援制度や支援機関との連携を積極的に進めることで、障がい者も安心して働き続けられる環境づくりが可能になります。
すべてを自社で完結しようとせず、支援機関などの外部機関と連携し、様々な制度を活用することが、持続的な障がい者雇用の実現するためのカギとなります。
障がい者雇用にお悩みの企業様は、ぜひ「はーとふる農園」のご利用もご検討ください。

お問い合わせ
ご質問、ご相談はお気軽にお問い合わせください